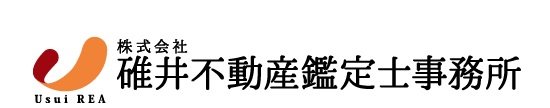継続賃料は、不動産事件の中でも、弁護士の先生にとって馴染のある分野かと思います。
私はこの分野が大好きでして、私的鑑定・公的鑑定の双方で多数鑑定を書かせていただいております。
この中で実感しているのが、『継続賃料は、結局1/2配分した差額配分法で決まるんでしょ』という認識を持ってらっしゃる弁護士の先生が(ベテランの方を含めて)結構多くいらっしゃることです。
これ、当たっている部分も有りますが、かなり危険な部分も有りまして…今回は、このテーマについて深堀りしてみたいと思います。
1.差額配分法(1/2配分)の発想
まず、差額配分法というのは、
- 現行賃料と新規賃料に差異があれば、これを収束させるべき
- 但し、『継続』なので、いきなり新規賃料と同じにするのは酷
- だから現行賃料と新規賃料の間で決めよう
という発想に基づく手法です。
そして、③の『間』の決め方として一番シンプルなのが、差額の1/2配分ということになります。
この様に説明されると、「なんとなくそうかな~」なんて思ってしまいますし、昔(H26年の鑑定評価基準改正前)は、『差額配分法は継続賃料の構造を的確に表す手法だ』的な説明もされていました。
実際、民民交渉ではこの発想が基本になっていて、
- 上げたい方/下げたい方が、「新規なら○○円だけど…」と言って来て、
- 上げられる方/下げられる方が、「それは分かってるけど、新規じゃないので…」と言い返して、
- 結局、「じゃあその真ん中で」という事で話が決まる
というのが王道パターンになっています。
2.法律的に考えてみると
上記はいったん置いておいて、賃料増減額交渉について法律的に考えてみますと、
- 法律上の賃料増減額請求が出来るのは、借地借家法上の『賃料増減額請求権』が発生しているから
- 借地借家法は民法の特別法なので、前提には『私的自治の原則』と『契約自由の原則』が存在する
- この中で賃料増減額請求権の性格を考えると、賃貸借契約が長期化しがちなことから生じる不具合を是正するための私的自治・契約自由の原則の修正条項となる
- とすると、直近合意はきっちり尊重されるべき(たとえ相場から高かったり安かったりしても)で、直近合意以降の事情変更によって生じた不具合を是正するのが賃料増減額請求権である
という風になります(参考に以下を引用します)。
松並重雄最高裁判所調査官「最高裁判例平成15年10月21日判例解説」法曹時報58巻4号212頁
借地借家法32条の賃料増減額請求権は,建物賃貸借契約が長期間に及び得るものであることから,公平の原則に基づいて認められたものであり,もともと,賃貸借契約開始後において,現行の賃料が「不相当となったとき」に爾後の賃料額の増減を認めるために設けられた規定である。
また,当初賃料額は,賃料相場等とは無関係に当事者が自由に決めることができるものであって,借地借家法が介入すべきものではないと考えられる。
この考え方に立ちますと、
- 貸すときにあまり知識が無かったのと、長く空いてて不安だったので、相場の6掛けくらいで貸してしまった
- 以降、周辺の賃料相場は横ばいだけど、この値段で貸し続けるのは辛い
というオーナーさんがいた場合、「このオーナーさんには賃料増額請求権は発生していないので、増額請求不可」という事になります。
3.訴訟の現場では?
賃料増減額請求が、実際の訴訟の現場でどのように捉えられているかですが、平成27年頃より大きく変わっています。
平成26年まで
継続賃料の訴訟になると、何らかの形で不動産鑑定士による鑑定書が提出される訳ですが、鑑定士の頭は『経済価値』をベースに動いていましたし、『私的自治』とかを意識している人はほとんどいませんでした。
この中で、鑑定評価書の中では差額配分法が重視される傾向があり、この発想が現実の実態とも合致していることから、法律的な建付はちょっと横に置いておかれた感じで、『継続賃料=差額配分法(1/2配分)で決まる』というイメージで動いていました。
但し、世の中の流れは『私的自治重視』になっていきましたし、平成15年から継続賃料について最高裁判例が蓄積されて、同分野についての判例ベースでの方向性が見いだせる様になって来ました。
平成27年以降
この様な中で、平成26年に鑑定評価基準の改正が行われました(平成26年11月1日受け付け以降のものに、この基準が適用されます)。
この基準改正の中で、継続賃料部分が大きく改正され、その内容は上記2.で書かせて頂いた賃料増減額請求権の法律的な構造を全面的に強調したものでした。
そうなると、鑑定士はそれに従わざるを得ませんので、訴訟で出てくる鑑定書も『直近合意の拘束性を基に、以降の事情変更による影響を判断して…』というスタンスになります。
結果、鑑定士として差額配分法を重視出来ない案件(直近合意賃料と賃料相場に大きな乖離が有る場合にそうなります)も出てきています。
ただ、改正の際の公式文書(改正基準を解説した実務指針)等もこの方向で書かれていますので、そのような鑑定書は訴訟の中で旗色が悪くなってしまっています。
4.以上の中での賃料増減額交渉への対応
以上により、現在の賃料増減額交渉は、民民交渉と訴訟等で価値基準が違ってしまっています。
ですので、法律的な構造を踏まえた訴訟における落としどころを踏まえつつ、どこまで踏み込むか(調停まではやる・訴訟まではいかない等)を戦略的に考える必要が有ります。
その意味において、今まで以上に弁護士の先生・クライアント様・鑑定士がチームを組んで、共通認識を持ちながら作戦を練っていくことが重要になっていると言えるでしょう。
※記事の内容に対するご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
携帯も利用可なフリーダイヤルを用意させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
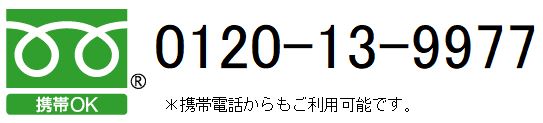
受付時間は、土・日・祝日を除く9:30 – 18:30となります。
メールでのお問合せはinfo@usui-rea.com(受付は365日・24時間)まで。